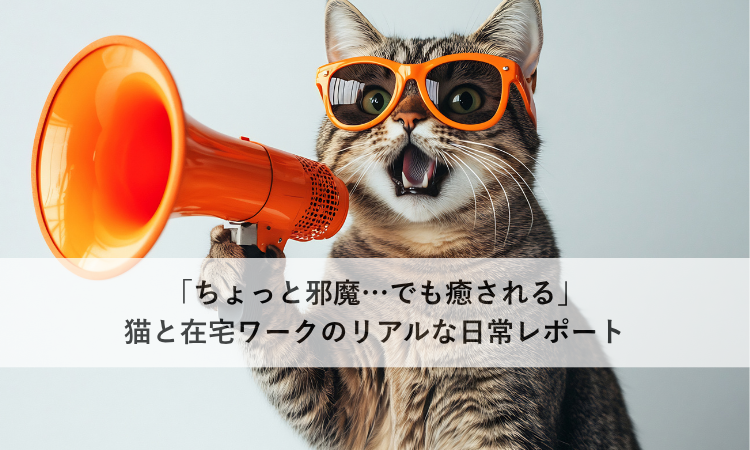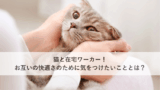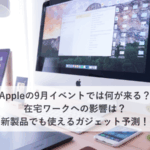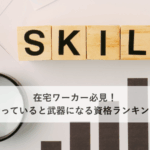はじめに──猫と在宅、相反する2つの効能「癒し」と「邪魔」をどう両立する?

在宅で働くと、猫は最高の「癒し」になります。
画面の横でまどろむ姿、ふとしたタイピング音に寄り添うゴロゴロ音(いわゆる“ゴロゴロ”の喉鳴らし)は、張りつめた神経をふっとほどいてくれる。
一方で、締切前にキーボードを横断、Zoomのミュートを解除、資料の上に鎮座……そんな「ちょっと邪魔」な瞬間も日常茶飯事。
本記事は、障がいのある在宅ワーカーや、その支援に関わる職員の方に向けて、リアルな日常の知恵をまとめました。
環境づくり/働き方/ツール選び/支援の視点を具体的にお届けします。
1:猫と人、どちらもごきげんで働ける「在宅レイアウト」のつくり方
1-1:作業動線と“猫動線”を分ける

猫は高い所・狭い所・見晴らしの良い所が大好き。
人の作業動線(キーボード・資料・マウス)と、猫の動線(昇り降り・巡回コース)を意識的に分離すると、キーボード横断が劇的に減ります。
- モニター横に専用の「見晴らし台」(浅い棚やラック)を設置
- 机の手前は人、奥の高台は猫、と縦方向にゾーニング
- 書類はクリアケースで垂直保管(上に乗れない)
こうしたキャットフレンドリーな環境はストレス軽減にも有効とされます。猫の本能(隠れる・見張る・よじ登る)を満たす工夫が鍵です。
1-2:“プレイス・オブ・イエス”をつくる
ダメな場所(キーボード・電源タップ)を増やすより、乗って良い場所を増やす方が現実的。
- カゴや箱を机上の隅に置く(猫は箱に吸い寄せられる)
- ブランケット付きのトレイで寝床を指定
- 日向の特等席(窓際の吸盤ベッド)を用意
「ここならOK」を先に提示すると、猫も学習しやすく、“邪魔の頻度”が下がる体感があります。環境エンリッチメントの観点でも理にかなっています。
1-3:ケーブルとガジェットの“噛み防止・落下防止”
- 束ねて浮かせる:ケーブルトレーや配線ボックスで床・机から距離を取り、噛みつき防止
- マグネット式充電:引っかけても外れる
- 重心の低いドリンク容器&ふた付きタンブラー:こぼし事故を予防
- ウェブカメラの物理シャッター:猫の“ミュート解除事故”時も安心
1-4:感覚過敏・注意切替が苦手な人への「視覚ノイズ」対策
猫の動きは可愛い=視覚的に強い刺激。
- デュアルモニターの片方に“集中画面”(全画面表示/通知オフ)
- ウィンドウ枠の太さ・配色を落ち着かせる(高コントラストは必要箇所のみに)
- 集中タイマーで“見る・見ない”の時間を分ける(後述のツール)
視線が猫に持っていかれる時間を意識的に“箱に入れる”イメージです。
2:在宅の“集中”と猫の“遊び”を両立する時間設計
2-1:プレイセッションは短く、回数で稼ぐ
5〜10分×3〜4回/日の短い遊びを散らすと、猫の満足度が高く、会議前後に切り替えがラク。
朝イチ・昼食後・夕方・就業後のルーティン化がおすすめ。
猫の狩猟本能に合わせ、薄暗い時間帯(明け方・夕暮れ)に1本差すのも効果的です。
2-2:遊び方のコツ——“獲物の筋書き”を用意する
- じゃらしは「逃げる→隠れる→再出現→捕まる」の順
- レーザーポインタ単体は挫折感を生むため、最後に実体のある獲物(小さなおやつやトイ)で“捕獲”体験を与える
- 箱・トンネル・布は“潜む舞台装置”に最適
この“捕まえさせる”エンディングが、猫の満足感=在宅の「邪魔」低減につながります。
2-3:休憩は「猫の世話」をトリガーにする
25分集中→5分休憩のリズム(いわゆるポモドーロ)を、休憩=猫ケアに紐づけると続きやすい。
- 水の交換/トイレチェック/撫でる・ブラッシング
- 窓辺のベッドを日差しに合わせて移動
- 短い“追いかけっこ”で体を温める
この“猫前提の休憩”は、心拍や呼吸を整え、再集中を助けます。
ペットと人の相互作用がストレス低減に資する研究も積み上がっています。
2-4:会議直前の“邪魔予防ルーティン”
- 5分前:高栄養おやつ・知育トイを設置
- 3分前:窓際ベッド or 高台へ誘導
- 1分前:ドアを半開き(出入り自由)
ちょっとした「先回り」で、会議中の乱入率は目に見えて下がります。
3:猫がいても“伝わる”在宅ミーティング術(アクセシビリティ対応つき)
3-1:自動字幕(キャプション)を迷わずオン

- Zoom:自動キャプションが無償アカウントでも利用可能。管理者による一括設定や、ホスト側での管理方法も公開されています。公式ヘルプを確認して設定しておきましょう。
- 公式:
https://support.zoom.com/の「Automated captions」「Managing automated captions」
- 公式:
- Google Meet:ライブキャプションに加え、直近30分をさかのぼってスクロールできる新機能が順次展開。翻訳キャプションにも対応(言語セットは更新中)。
- 公式:
https://support.google.com/meet/(例:/answer/15077804ライブキャプション、/answer/10964115翻訳キャプション)
- 公式:
聴覚支援が必要な方、雑音が苦手な自閉スペクトラムの方、外国語話者の方にとって文字情報の並走は強力な安心材料です。
3-2:音と背景——猫の“生活音”を味方にする
- Microsoft Teamsの「Voice isolation」やノイズ抑制で、猫の食器音・鈴の音を軽減。背景は標準ブラー/ポートレートブラーへ。
- 公式:
https://support.microsoft.com/の「Voice isolation」「Change your background」参照
- 公式:
3-3:緊急“猫乱入”プロトコル
- キーボードカバーで強制入力を回避
- ミュートの物理ショートカットを習慣化(会議アプリごとに確認)
- カメラの物理シャッターで“猫のドアップ”を回避
- チャットに「猫が通過します」テンプレを用意(支援職・同僚間で共有)
予め“起こりうる前提”として備えると、恥ずかしさも実害も最小化できます。
3-4:視線共有の工夫——資料は「見失わないUI」に
猫が画面前を横切っても大丈夫なように、
- 字幕ON+発言者の自動ハイライト
- マルチピン/マルチピン留め(発表者+手話通訳者など)
- チャットに要点を逐次テキスト化(聞き逃した人がすぐ追いつける)
「映像だけに頼らない」会議設計が、多様な感覚特性への配慮になります。
4:仕事の“集中”を守るツールと、猫の“満足”を高める仕掛け
4-1:集中・時間管理
- Google カレンダー(予定ブロックで「猫ケア」も予約)
公式:https://calendar.google.com/ - Notion(猫ケア・仕事・休憩を1ページで可視化)
公式:https://www.notion.so/ - Forest(スマホ集中タイマー)
公式:https://www.forestapp.cc/ - Zoom/Google Meet/Microsoft Teams(字幕・ノイズ抑制・背景)
公式:https://zoom.us//https://meet.google.com//https://www.microsoft.com/microsoft-teams/
4-2:猫の環境エンリッチメント
- International Cat Care(猫に優しい住環境・遊びの指南)
公式:https://icatcare.org/ - FECAVA(屋内猫のエンリッチメントのまとめ)
公式:https://www.fecava.org/
4-3:心の健康——“猫の癒し”を仕事の回復に変える
- HABRI(Human Animal Bond Research Institute)のレビュー・ブログで、ペットと人の相互作用がストレス軽減/幸福感向上に寄与する知見を学ぶ
公式:https://habri.org/
5:体験談・インタビューから見えた“リアル”——ケース別ミニ・シナリオ

※当ブログ読者の声・オンライン座談会の要約です(個人が特定されないよう編集)
5-1:注意切替が苦手(ASD特性)×保護猫2匹
- 困りごと:視界の端での高速移動(猫ダッシュ)で集中が切れる
- うまくいったこと:“集中タイムは遮光カーテン半分+机上ブランケットの巣”で猫の居場所を固定/短時間×高頻度のじゃらし遊びに変更
- 効果:猫の“仕事中アピール”が減少、午後の再集中が安定(本人談)
参考:短時間のプレイセッション推奨・舞台装置の活用。
5-2:感音性の過敏(聴覚過敏)×在宅コールセンター
- 困りごと:猫の食器音・鈴音が通話に乗る/自分も疲れる
- うまくいったこと:Teamsの「Voice isolation」で相手側に雑音が乗らない/自分は耳栓+片耳ヘッドセットで負荷を分散
- 効果:平均処理時間が改善、終業時の疲労感が軽減(上長評価)
参考:TeamsのAIノイズ抑制と背景ぼかし。
5-3:聴覚障がい当事者×海外チームとの定例
- 困りごと:アクセントが強い英語の会議で情報を取りこぼす
- うまくいったこと:Meet/Zoomの自動字幕+翻訳キャプションで発言を追う/会議後、キャプション履歴を30分スクロールして要点回収
- 効果:議事の取り逃しが減り、在宅でも共同作業の“同時性”を担保
参考:Google Meetの字幕履歴のアップデート、Zoomの字幕機能。
5-4:発達性協調運動障がい×ケーブル事故多発
- 困りごと:足元の配線に引っかかる/猫もつられて遊ぶ
- うまくいったこと:配線を“浮かせる”レイアウト+マグネット式給電/机上の“猫席”で移動の興味を固定
- 効果:転倒リスク低下、猫の“コード噛み”消失(家計も平和)
5-5:おまけ・筆者の場合
私も精神障害を抱えながら猫と同居して在宅ライターをしています。
長毛の猫なので綿毛が部屋中に舞うのが悩み。
作業部屋を完全に個室化し、猫が入れないようにすることで電気系統への毛の干渉を防いでいます。
ですが、作業中に猫が部屋のドアをカリカリと引っ掻き寂しそうな鳴き声で呼んでくることも。
そんな時はトイレに行くついでに撫でてあげたり、軽く遊んであげます。
たったそれだけの時間でも、猫にとっては満足になるようです。
まとめ──「邪魔」も「癒し」も、設計すれば味方になる
- 環境:人の動線と猫の動線を分け、“プレイス・オブ・イエス”を用意
- 時間:短時間×複数回のプレイセッションで満足度UP、会議前は先手ケア
- 会議:自動字幕・翻訳・ノイズ抑制・背景ぼかしを標準装備に
- 支援:職員・同僚は「猫は在宅の前提」と捉え、テンプレ文や議事のテキスト化で情報保障
在宅の強みは、自分と猫の“最適解”を家庭内で設計できる自由度にあります。
「ちょっと邪魔…でも癒される」——この両輪をうまく回すと、生産性も満足度も上がります。
あなたの在宅ワークに、今日から取り入れられる猫との共存の一歩をぜひ。
合わせて読みたい
在宅ワーク中の猫に関するトラブルについてはこちらの記事でも紹介しています。
ぜひ合わせて読んでみてください!