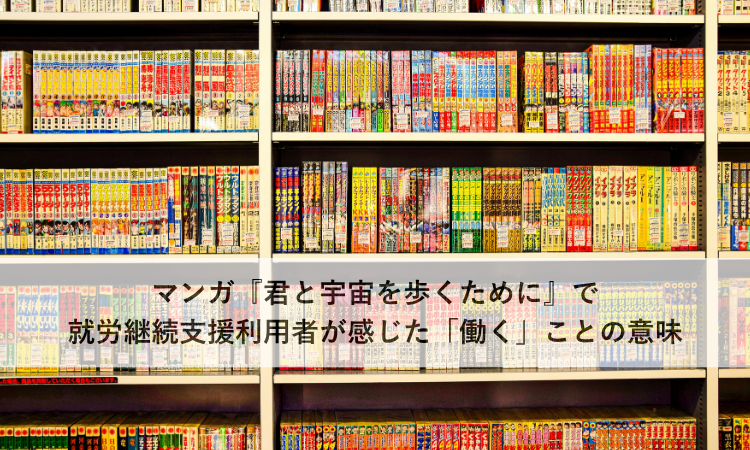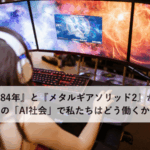んにちは。就労継続支援A型事業所で働いているKです。
私は今、支援のある環境で少しずつ働くことに向き合っています。
「働くことがつらい」「人とうまく関われない」「自分は何ができるのか分からない」
そんな気持ちを抱えながら日々を送っている中で、ある漫画に出会いました。
それが、泥ノ田犬彦さんの『君と宇宙を歩くために』です。
この作品は、私が「働く」ことについて悩んでいた時期に読んで、とても心に残った作品です。
今回は、“働くことが難しい”と感じている人にもぜひ読んでほしい、この作品の魅力と、私自身が感じたことをお伝えしたいと思います。
『君と宇宙を歩くために』とは?
『君と宇宙を歩くために』は、泥ノ田犬彦(どろのたいぬひこ)さんによる漫画作品で、講談社のWebコミックサイト「&Sofa」で2023年より連載がスタートした話題作です。現在(2025年10月時点)では既刊4巻が発売され、「マンガ大賞2024」の大賞受賞をはじめ、数々の漫画賞を獲得するなど、高い評価を得ています。
この作品は、「生きづらさ」を抱えた若者たちが、懸命に“自分の歩き方”を模索していく物語です。
見た目ではわからない「困りごと」がある
主人公の1人、小林大和は、金髪で大柄、ヤンキーっぽい風貌。けれど、彼は何か特別に悪いことをしているわけではなく、ただ「勉強が苦手」「バイトが続かない」「何が向いているのかわからない」という悩みを抱えています。
一見すると、「やる気がない」「不真面目」と誤解されやすいタイプですが、彼の苦しみは決して怠惰などではなく「できないことが多い」という切実な現実から来ているものです。
もう1人の主人公、宇野啓介は、小林とは真逆。落ち着いた雰囲気で、宇宙に詳しい知識を持つ少年。けれど、人との関わり方に不安を抱えており、大きな音や急な予定変更が苦手です。彼は「困ったときのためのノート=テザー」を作り、それを頼りに毎日を過ごしています。
2人とも、周囲から「普通」だと思われている基準にうまく適応できない。でも、その理由を誰にも説明できない。「怠けてるだけ」と言われてしまう。
この「説明できない生きづらさ」の描写が、なんともリアルなのです。
名前をつけないからこそ届く“フラットな”視点
この作品では、主人公たちに明確な診断名は登場しません。あくまでそれは読む側が感じ取ることであり、作中で明言されることはありません。
この「名前をつけない」という選択は、読む人の偏見を防ぎ、「これは他人ごとではない」と気づかせるための工夫なのだと思います。
つまり、「誰でも、生きづらさを抱えている可能性がある」ことを伝えているのです。
“がんばる”のではなく、“一緒に歩く”
本作のタイトル『君と宇宙を歩くために』にある「宇宙」とは、決して壮大な宇宙空間のことではありません。
それは、日々を生きるこの世界そのもの。そして、「何が起きるかわからない」「一人では不安でたまらない」世界でもあります。
宇野は、そんな“宇宙”を歩くために、自分なりの方法(ルール、ノート、習慣)を身につけてきました。小林は、それを最初は「変わってるな」と思いながらも、次第にその工夫を理解し、自分自身の困難にも向き合うようになっていきます。
2人は、誰かを“支える”とか“助ける”関係ではありません。
それぞれが抱える困難を「理解しようとする」、そして「無理に変えようとはしない」、その姿勢こそが、現代社会に必要な「共に生きる」ヒントなのではないでしょうか。
恥ずかしさの殻を破る、その一歩の尊さ
物語を通して、印象的に描かれるのは「恥ずかしさ」との付き合い方です。
自分が周囲と違うと気づいたとき、誰もが「恥ずかしい」と感じるものです。
その感情にとらわれて動けなくなってしまうこともあります。
けれど、『君と宇宙を歩くために』では、その「恥ずかしさ」を“悪いもの”としては描きません。
宇野も小林も、少しずつ勇気を出して、「わからない」「できない」「助けてほしい」と口にしていきます。
例えば、小林は自分の不器用さからアルバイト先でミスをし、距離を置いてしまった先輩たちに対して、 宇野との関わりを通じて少しずつ自分の感情と向き合い、謝罪の言葉を伝える決意をします。
「うまく言えないかもしれないけど、ちゃんと話してみよう」――
その一歩は、決して派手ではないかもしれませんが、
自分の殻を破り、もう一度人との関係を築こうとする小さな勇気の象徴です。
こうした行動が、やがて周囲の理解を生み、自分の中の「ちょっとした誇り」へと変わっていきます。
それは、小さくても確かな“前進”であり、「自分のペースで歩いていいんだ」と読者に教えてくれるのです。
「働くこと」へのプレッシャーと自分らしい歩み方
「働くこと」について考えるとき、どうしても「がんばることが正しい」「みんなと同じようにやらなきゃ」といったプレッシャーを感じてしまうことは、結構あります(私がそうです)。
けれど、『君と宇宙を歩くために』を読んで感じたのは、“働く”というのは、一人で完璧にやりきることではなく、誰かと共に自分のペースで関わっていくことでもある、という視点です。
私自身、A型事業所という環境のなかで、支援員さんや仲間と関わりながら働く経験をしてきました。
その中で学んだのは、「支えてもらいながら働くこと」や「わからないことをそのままにしないこと」も、大事なスキルだということです。
“社会に出る”とか“自立して働く”という言葉は、ときに重く感じられるかもしれません。
でも、最初の一歩は、「誰かと一緒に歩くこと」でもいいはずです。
まとめ:「宇宙に放り出されたような感覚」を知っている人へ
私たちは時に、「この世界に居場所がない」と感じる瞬間があります。
人がたくさんいるはずなのに、誰にも理解されていない気がして、まるで“宇宙に放り出されたような感覚”に襲われることがあります。
働くこともまた、そうした感覚と地続きにある営みです。
職場での人間関係、自分の役割がわからない不安、失敗の記憶。
それらが重なると、「もう一度関わる」ことがとても怖く感じられる。
ですが、この物語には
「一人じゃなくてもいい」
「わからないままでも歩き出していい」
という、静かであたたかなメッセージが込められています。

(写真 Canva)
そして何より大切なのは――
“君と宇宙を歩く”という行為そのものが、すでに生きていることの証であり、意味であるということ。
必要なのは、誰かと比べて変わることではなく、
「自分のペースで、自分らしく、もう一度つながりを結びなおすこと」かもしれません。
この作品が、あなたが「働くこと」や「人と関わること」に迷ったとき、その一歩にそっと寄り添う道しるべとなることを願っています。
最後に:さらに深く「働く」ということを考えたい方へ
今回ご紹介した『君と宇宙を歩くために』は、「生きづらさ」や人との関わりのリアルを繊細に描いていますが、同じテーマを異なる角度からも描いている作品として、『シュリンク-精神科医ヨワイ-』というマンガ作品もおすすめです。
『シュリンク-精神科医ヨワイ-』は精神障害を抱える人々の挑戦を丁寧に描き、多様な背景を持つ登場人物たちのリアルな葛藤と成長を追っています。医療的な視点だけでなく、社会の偏見や職場環境、支援のあり方まで幅広く描かれており、多くの人に共感と気づきを与えてくれます。その中で、彼らが「働く」ということについても丁寧に描写されていますので、もし今回の作品に共感したり、もっと多角的に「生きづらさの中で働くこと」について知りたいと思ったら、ぜひこちらの記事もご覧ください。
- 精神障害のリアルを描くマンガ『シュリンク-精神科医ヨワイ-』にみる「働く」という挑戦
精神障害者雇用制度や実際に働く際の課題(合理的配慮等)について深く掘り下げています。 - 精神障害のリアルを描くマンガ『シュリンク-精神科医ヨワイ-』にみる「働く」という挑戦 PART2(こちらは近日公開予定です)
発達障害、パーソナリティ障害、薬物依存症を抱える人々の物語と、その挑戦から見える「働く」意味について考察しています。
「働くこと」にはいろいろな形があります。この作品を通して、あなたが自分の気持ちに寄り添いながら、自分らしいペースで歩いていくためのヒントが見つかれば幸いです。
あせらなくて大丈夫。