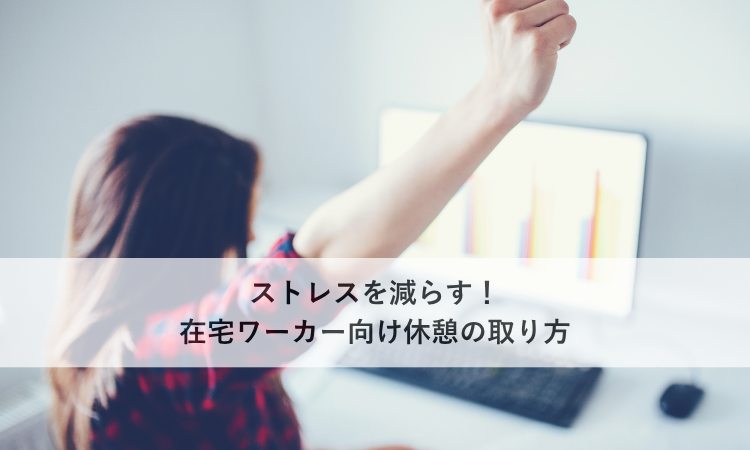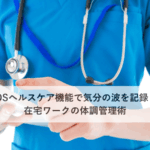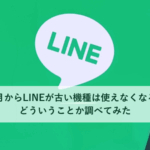はじめに
在宅ワークは自由度が高く、「在宅で働きたい」という方は最近増えています。
しかしその反面、
などの悩みも少なくありません。
特に障がいをもつ方が在宅で働く場合、体調管理は最も重要です。
本記事では「在宅ワーク中にどう休憩を取るか」を切り口に、ストレスを軽くし、効率と心身のバランスを両立させる休憩方法をまとめました。
小さな工夫の積み重ねが、日常をグッと楽にしてくれるはずです。
休憩の”カタチ”を考える

「休憩」が重要な理由
在宅勤務では、オフィスのような強制的な区切り(昼休み、移動時間、同僚との雑談など)が弱くなりがちです。そのため、意識的に休憩をとらないと、疲れやストレスが徐々に蓄積してしまいます。
長時間の座りっぱなしは健康リスクを高めるという研究もあり、定期的に休憩を挟むことが体と心を守るうえで不可欠です。
さらに、
などの効果もあります。
逆に、休憩なしで仕事を続けると効率が下がったり、やる気が出なくなってしまいがちです。
おすすめの休憩のカタチ
休憩法としてよく知られているのが「ポモドーロ・テクニック」です。
これは作業と休息を区切るテクニックで、集中力を維持しやすいことで知られています。

wrike.com+4WEB会議DEどうでしょう+4ツギノジダイ+4
このテクニックは集中力の維持だけでなく、疲れすぎる前に休憩がとれるため、作業の区切りをつけにくい在宅ワークの方にとても有効です。
もちろん、常にすべての作業にこのカタチが合うわけではありません。
作業によっては中断しづらいタスクもあるかと思います。その場合は「50分作業+10分休憩」など、作業に合わせた調整も可能です。
大事なことは「こまめに休憩をとること」です。
wsf-is.com+1
休憩のタイミングをつくる
「休憩は大事」とはいえ、つい後回しにしがちな方もいます。
そういう方には「自然な切れ目」で休憩を入れるのがおすすめです。
このように「決めたタイミングで休憩」とルールをつくっておくと、気持ちの区切りをつけやすくなります。
「時間で区切る」か「タイミングで区切る」のか、自分の性質に合わせてやりやすい方法で休憩をとりましょう。
休憩時間の過ごし方のコツ

休憩時間はただ「手を止める」だけでも効果がありますが、「体を動かす休憩」と「静かに自分を整える休憩」を使い分けることが大事です。
体を動かす休憩
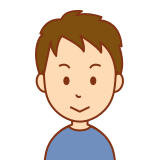
ずっと同じ姿勢でいると、体が痛くて……
作業に集中していると「座りっぱなし」や「画面を凝視」などで痛みやこわばりを感じてしまいますよね。そういう場合には、休憩中に軽いストレッチを取り入れましょう。
これらは道具も広い場所もいらないので、気軽に試せます。
簡単な動作でも筋肉や血流がリセットされ、目の疲れも軽減できます。
特に長時間の作業中には、1時間に1回程度のストレッチがおすすめです。
wrike.com+3サーブコープ+3シンビーオ | 在宅で広がる可能性。障害があっても活躍できる社会へ+3
また、「20-20-20ルール」も目の疲れを解消する方法として知られています。
20分ごとに、20フィート(約6m)先を20秒間見るというもの
静かに自分を整える休憩
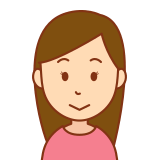
とにかく疲れを感じる……
そういう場合には、心と頭を落ち着かせるための「静かな休憩」をしてみましょう。
こういった休憩はリラックス効果が高く、ストレス軽減に大きな効果があるという研究結果も出ています。arXiv+1
自分に合った休憩方法を
疲労具合・作業内容・体調によって必要な休憩は変わってきます。
たとえば「朝は体が硬いからストレッチを多めに、午後は静かにリラックスする」など、自分なりの「休憩ルール」をつくっておくと良いでしょう。
心にも休息を

疲れるのは体だけではありません。
頑張った分、同時に心も疲れていってしまうので「心を休める」ことも大事です。
意識して「肯定」する
休憩中に、今日の「よかった点」を3つ挙げてみましょう。ノートに書いてもいいですし、心の中でめいっぱい褒めるのもOKです。「できたこと・嬉しかったこと」などささいなことでかまいません。
疲れが溜まると人はネガティブになりがちです。
小さな「肯定」の積み重ねが、ネガティブ思考から一歩離れる手助けになります。
“脱デジタル”の時間をつくる
画面をずっと見続けていると、目の疲れだけでなく“情報過多”による脳の疲れも起きやすくなります。
そこで、手書きのメモやスケッチなど「アナログな手段」に触れることをおすすめします。
例)休憩中に日記を1行書く
今日のタスクを手書きしてみる
情報のインプットだけでなく、自分の手を動かしてアウトプットすることが大事です。
完全オフの時間をつくる
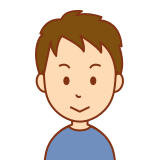
休憩中だけどチャットの返事が気になる……
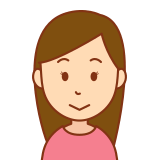
作業のことを休憩中にも考えちゃう……
そういう「頭が休まらない」方には、「完全にオフ」の時間をつくることが必要です。

こうした方法で、身体的にも心理的にも“切り替える”時間を作ることが、ストレス対策に有効となります。Indeed+4sangyoui.m3career.com+4PCA+4
休憩のルールとツール

「休憩しようと思っても、つい先送りしてしまう……」という方向けに、休憩ルールの決め方と、それに役立つツールをご紹介します。
休憩ルール
こうして事前に決めておくことで、休憩の先送りを防止することができます。
ツール・アプリを活用する
先ほどのルールを全部自分で管理するのは大変ですよね。そんな時に役立つおすすめツールをまとめました。ツールによって無料・有料とありますので、自分に合ったものを選びましょう。
- Focus To-Do
ポモドーロ・テクニックとタスク管理を統合したアプリ。
集中時間と休憩時間を設定でき、タスクと時間の統計も取れる機能もあります。Apple - gogh(ゴッホ)
アバターとともにポモドーロ・テクニックの集中セッションを行えるアプリ。
集中時間と休憩をビジュアルで演出してくれる点が人気です。ゆるりと - カズサイのWEBポモドーロタイマー
ブラウザで即使えるシンプルなポモドーロタイマー。
インストール不要で、どの端末でも使える手軽さが魅力。ゼロからAI副業 - その他時間管理アプリ
さまざまな時間管理・集中ツールが紹介されています。VoicePing 2.0
なかなか説明だけでは自分に合ったものを見つけるのは難しいですよね。
とりあえず試しに無料のツールを使ってみるのもおすすめです。
ツールを使ううえでの注意点
アプリやタイマーはあくまでサポートです。
使い始めで「休憩をとる・止める」がストレスになるようなら無理は禁物です。また、ポモドーロ・テクニックがすべての人、すべてのタスクに合うわけではありません。
うまくいかなかった場合には無理せず、ほかの方法を試してみましょう。ツギノジダイ
まとめ:自分に合う休憩ルールを育てよう
休憩は自分に合った「カタチ」を見つけることが大事です。
- 休憩のカタチ:ポモドーロ・テクニックや50分+10分などの休憩リズム
- 動く休憩 or 静かな休憩:軽いストレッチ、深呼吸や瞑想などを体調に合わせてとる
- 心の休息:デジタルから離れる、自分を肯定する
- 休憩ルール:スケジュール・タイマーなどで休憩の予定を事前に立てる
- ツールを活用:Focus To-Do、WEBタイマーなど、自分に合うものを選ぶ
休憩は「サボり」ではなく、仕事の質と心身の健康を支える大事な時間です。
仕事を継続していくためにも、休憩を大事にしていきましょう。