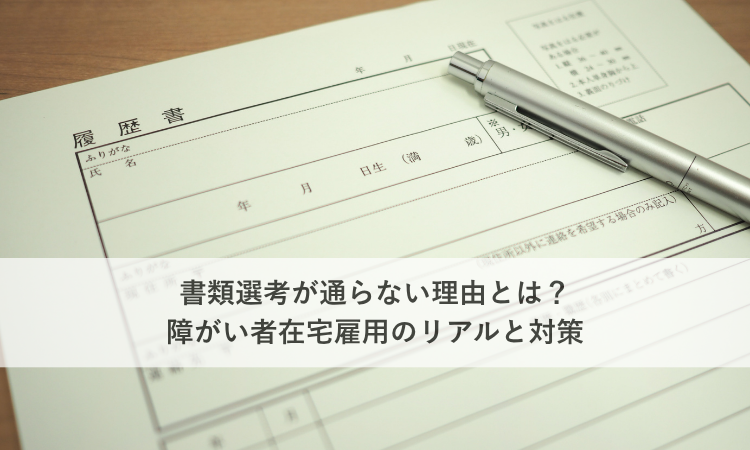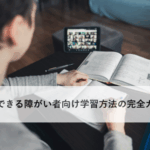はじめに
在宅ワークの広がりに伴い、障がいのある方にとっても就労の選択肢が増えてきました。
しかし「何社応募しても書類選考が通らない」と感じる方は少なくありません。
特に在宅雇用の求人では、企業側が求める条件が明確である一方で、応募者がそれを正確に伝えきれないケースも多いのが実情です。
この記事では、「なぜ書類選考に通らないのか?」という疑問に対して、実際の在宅障がい者雇用の現場で起きている課題とその背景、そして改善のための具体的な対策について解説します。
ご自身の強みを正しく伝え、次のステップへ進むためのヒントにしてください。
書類選考が通らない主な理由とは?
1. 応募書類に「在宅で働く」理由が書かれていない
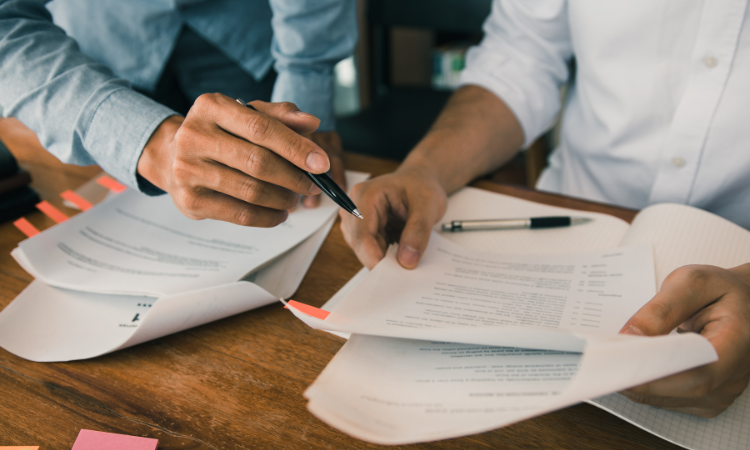
在宅で働く希望を出す場合、企業はその理由を重視します。
単なる「通勤が難しい」という記述ではなく、「在宅であれば自身の持つ○○のスキルをより発揮できる」など、前向きな理由や生産性の高さにつながる視点が求められます。
対策:
- 就労希望理由欄に「在宅の方が集中できる」「通院・体調管理との両立がしやすい」といった具体例を。
- 必要であれば、医師の診断書の内容を反映した自己申告も添える。
2. 職務経歴書が「成果」より「作業内容」中心
「入力業務をしていた」「事務作業を担当した」など仕事内容を淡々と並べるだけでは、採用担当者に魅力が伝わりません。
特に在宅雇用では、自主的に仕事を進められる人材が重宝されるため、成果や改善事例の記載が重要です。
対策:
- 「Excelでの作業効率を20%向上させた」など数字での実績を記載。
- チームでの業務分担や、主体的に動いた経験を明記。
3. 障がい内容の伝え方が不十分または不適切
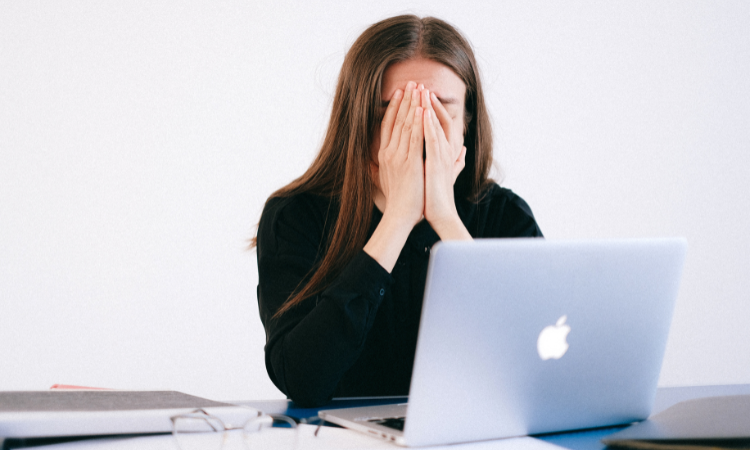
配慮事項が多すぎるように見えたり、逆に情報が少なすぎて企業が不安になるケースも。
どんな配慮が必要で、どのような業務が可能かを簡潔に伝えるバランスが必要です。
対策:
- 医療情報に立ち入らず、働く上で必要な配慮事項とできる業務内容をセットで伝える。
- 配慮事項だけでなく、「自分で工夫している点」もプラスして印象アップ。
障がい者在宅雇用の現場で見えてくる「企業側の視点」
1. 在宅=自由ではない、自己管理力が最重視
「在宅なら気軽」と思われがちですが、実際は自己管理能力や報連相スキルがより重要になります。
企業は、物理的に見えない環境でも「信頼できるか」を厳しく見ています。
企業が重視している点:
- 1日あたりの稼働時間の安定性
- 業務報告や連絡の正確さ・速さ
- ネット環境やPCスキルの基本
2. 業務とのマッチングが厳しい

在宅ワークは「完全成果型」の業務が多く、汎用的なスキルでは通用しないことも。
例えば、データ入力ひとつ取っても、「タイピング速度」「Excel関数スキル」「業務理解力」などが求められることがあります。
企業側のチェック項目:
- 希望職種に対する実務経験の有無
- スキルシートやポートフォリオの有無
- 「自分で調べて動けるか」という姿勢
書類選考通過率を上げるための実践ポイント
1. 履歴書・職務経歴書は「自分の武器」を明確に

何ができて、どのように貢献できるのか。
スキルや経験を「応募先の仕事内容に合わせて」書くことで、採用担当者に届く書類になります。
ポイント:
- 汎用フォーマットではなく職種別に書類を最適化
- 表現は簡潔に、実績ベースで
2. 支援機関のアドバイスを受ける
一人で悩まず、就労支援機関や相談窓口を活用することで、書類の添削や面接練習、求人紹介まで対応してもらえます。
主な支援機関:
- 【障害者就業・生活支援センターについて】(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html - 【LITALICOワークス】(民間支援)
https://works.litalico.jp/
3. オンラインポートフォリオで実力を見せる
特に在宅でのクリエイティブ職やIT職を目指す場合、オンライン上で実績を見せられるポートフォリオが強みになります。
おすすめツール:
- 【Notion】https://www.notion.so/
- 【Google Sites】https://sites.google.com/
よくあるQ&A
Q:障がいの種類によって不利になることはありますか?
A:職種や企業によって求める能力が異なるため、配慮内容とのミスマッチがあれば不利に働く可能性はありますが、それ以上に「仕事への適性」と「正確な情報提示」が重要です。
まとめ:在宅ワーカーとして「伝える力」が突破のカギ
障がい者雇用において、書類選考はただの通過点ではなく、「自分の仕事力を伝える第一関門」です。
企業側も、「在宅で本当に任せられる人か?」という視点で慎重に選考しています。
だからこそ、応募書類は“誤解を生まない丁寧な自己紹介”であるべきです。
スキルと配慮事項、そして前向きな姿勢をわかりやすく伝えることで、少しずつ選考通過率を高めていけます。
「通らない理由」を責めるより、「伝えきれていない部分があるかも」と見直すことから、次のチャンスが生まれます。
今できる最善の準備で、一歩前へ進んでいきましょう。